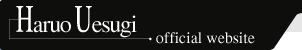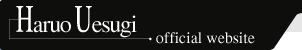「耳で聴く情景」
虫のすだく音を聴いていても、ある人にとってはすばらしい音楽、ある人にとってはただの騒音に聞こえます。
このように、音が我々の脳の中に伝えられて初めて「音楽」になるのです。我々一人一人の「外側」に音楽があるのではありません。
脳で美しい音楽と感じられた時、その「美しさ」は、例えばすばらしい風景や、絵画を見たときに感じる「美しさ」と違うものでしょうか?僕はそうは思いません。だからこそ、美しい音楽を聴いて、絵画や、様々な情景を思い描くことが出来るのだと思います。ここにおいては、美しいという感情を接点として、聴覚と視覚が互いにつながっているのです。
視覚だけではありません、音楽を聴きながらいろいろな記憶をよみがえらせる、踊っているような気持ちになる・・・音が脳の中に入ってくるところから始まって、実に様々な働きが起きます。音楽を聴く感動というのは、そうした働きの中に、あるいは、働きの総和にあるのではないでしょうか。
今日の演奏会では、題名のついた曲ばかり選んで見ました。作曲家が音の向こうに実際の絵であれ、心象風景であれ、何かの情景を見ていた、そういうことがわかる作品群です。でも、詳細に調べてみれば、作曲家は決して元になっている文学作品や絵画などに縛られて曲を書いているのではなく、目で見たことから引き起こされる自由な発想を音にしたものだということがわかってきます。
どうか皆様も、曲の題名や解説をよりどころに、しかし自由にいろいろな発想を膨らませて聴いてください。それが感動の源なのですから・・・もしさらに、音の向こうに等身大の作曲家の、時代と人種を超えて我々と直接共感しあえる何かを感じていただけたら、とてもうれしく思います。音楽を聴くという行為を通して得られるもの、それは普段気づかない自分自身の姿を発見することに他ならないのです。
メシアン:前奏曲集より
メシアン(1908-1992)は、20世紀中期以後を代表するフランスの大作曲家です。
この前奏曲集は弱冠20歳頃に書かれたもので、後年の作品集に比べればリズム探求など未完成な点は否めませんが、それでも彼自身が「青みがかった色」と呼ぶ独特の音群(音を色で感じるというのは多分に主観的な判断によるもので、個々人が実感できないのであればあまり拘るのはよくないと思いますが)の使用や、神秘的な響きに陶酔しながらも常に透明感のある明るさに満ちているあたり、すでに明らかにメシアン独自の世界が出来上がっていることに驚かされます。
同時に、詩的なタイトルや、2度、4度(増4度)と言った音程が作り出す音色感の変化を追及する姿勢などには、後期のドビュッシーの影響も窺われます。
この曲は1929年に出版され、翌年曲集を捧げられたパリ国立高等音楽院の同級生、アンリエット・ロジェによって初演されています。そのときのメシアンからの唯一の注文は「桃色と白い服では演奏しないこと。できれば青か緑を」ということだったそうです。若いメシアンの、色彩へのこだわりだけでなく、パリ音楽院で6部門に1等賞ととった才媛・ロジェ嬢に恋心を感じていたのではないか、そんなことも感じさせるさわやかなエピソードです。今回プログラムのバランス上割愛いたしました他の曲(悲しき風景の中の恍惚の歌、過ぎ去りし時、苦悩の鐘と別れの悲しみ)もすばらしい作品ですので、ぜひ機会があれば聴いてみてください。
1. 鳩
後年世界中の鳥の鳴き声を採取し、楽譜化して楽曲内で使用したほど、メシアンにとって鳥の鳴き声は特別な意味を持っておりました。しかし、ここでは直接的な鳴き声の模写はあまり見られず、ゆったりと上下する音程などに象徴的に鳩が表現されているようです。神、聖霊の象徴としての鳥に対する敬意もそこには込められております。
開始のF-Hの増4度音程は、この曲集を支配する響きです。
3.軽やかな数字
数は、そのまま音、音程につながります。またここでは韻ということも念頭におかれているようです。
極端な高音にも低音にも至らず、中音域でふわふわと浮遊する音たちは、まさに無重力の軽さを表しているようす。後半は高音部と低音部がカノンで掛け合いますが、最後にカノンの重力から解放され、高みに登っていきます。
5.夢の中の漠然とした響き
左手の和音は「青色がかったスミレ色」の響きが使われています。右手の響きには「赤紫の」色彩が使われており、“漠然とした”響きではありますが、全体に非常に華やかな印象を与えます。中間部の高音と低音で上下ひっくり返ったカノンは、中声部の密集音程によってかなり黒ずんだ灰色の背景をつけられております。
7.静かなる不満
最初の5度―増4度の響きに象徴されるように、さまざまな音程の移り変わりと色彩感の微妙な変化が美しい曲です。基調となる色彩は灰色で、そこに赤紫と緑が見えます。
8.風に映る影
ドビュッシーの「水に映る影」を意識したタイトルでしょう。ピアノ奏法上からは、リストーラヴェルの影響が感じられます。
旋律の背景には、常に薄青色の風が吹き抜けております。
リスト:巡礼の年報第一年「スイス」より、“オーベルマンの谷”
リスト(1811-86)は、19世紀ヨーロッパを代表するピアノの名手でした。若い頃は行く先々で圧倒的な人気と評判を呼び、演奏中に失神する若い女性がいたといいますから、今で言えば全盛期のビートルズとか、ヨン様なみのスターだったと推測されます。
そのリストが24歳の時、既婚者である伯爵夫人と駆け落ちをするという事件を起こしました。二人はパリを出てスイスで落ち合いしばらくそこに滞在します。その時に書かれた作品集「旅のアルバム」を20年後にまとめなおしたものが、ピアノ曲集「巡礼の年報第一年・スイス」です。「オーベルマンの谷」は中でもっとも規模が大きく、中核をなす作品です。
オーベルマンというのは、1802年に出版されたフランス人作家セナンクールの90もの書簡からなる小説「オーベルマン」の主人公です。この曲のタイトルの中にある「谷」も、セナンクールの作品中スイスアルプスの自然を描写する折々に出てきます。
セナンクール自身家族を相次いで無くし、貧困にあえぎながらこの作品を書いたと言われております。彼の分身であるオーベルマンも、スイスの自然と、その向こうに存在する神に一体化することで救われようとした、一種の自殺願望を持つ人物として書かれていますが、そのどこに大スター、リストは共感したのか・・・
リストは自筆原稿冒頭にセナンクールの「オーベルマン」の長大な引用を書いております。一部を書きますと
「・・・自然のかくも広大で計り知れないものであること、宇宙の情熱、冷淡なまでの中立性、我々の想像もつかぬ叡智などを広く意識したとき、人類が心に留め得るすべての欲望や苦しみを私は感じ、受け止める・・・私は衰弱への不吉な一歩を印してしまった。私の10年は失われた」
大スター・リストであっても、いや、大スターと世間からは見られれば見られるほど、実際の自分の小さな存在に絶望する時があったのかもしれません。
曲は、低い音がさらに下に、下に沈んでいくような旋律で始まります。何度も上に上がる努力を繰り返しながらも常に下に引きずられるメロディ。やがて、天上の音楽のような美しい旋律が上から降ってきますが、自らはまだそれに一体することができず、ただあこがれて見上げるばかりです。
その後激しい葛藤と戦いが行われ、傷ついた心を慰めるような優しい音楽が聴かれます。そして、ついに下への重力に負けていたメロディが、上へと向いて、あとは勝利を高らかに歌い上げていく・・・
こうしてみると、多大の共感を持って書かれたとはいえ、やはり現実の世の中においては成功者であった若いリストには、最後に絶望的な運命に打ち勝とうという意気込みが強かったのでしょうか。音楽を見ると、小説のあきらめに似た境地とは違い、広大な山々を前に、谷底にたたずむ無力な人間が、ついに自らの力で高みへと登り行く心象風景が描かれているような気がしてなりません。
ラヴェル:鏡より “鐘の谷”
ラヴェル(1875-1937)30歳頃の作品、ピアノ曲集「鏡」は、“蛾”、“悲しい鳥”、“大海原の小舟”、“道化師の朝の歌”、そしてこの“鐘の谷”からなります。「鏡」とこれらのタイトルにはどういう関係があるのでしょう?
鏡を見たときに映るものは、自分の姿です。鏡の中で無軌道にバタバタと飛び回る蛾、帰り道を見失ってさまよう熱帯の鳥、大波に翻弄されるたよりない小船、スペインの道化(ラヴェルの母親はスペイン出身)・・・そう、これらはラヴェルの自画像なのではないでしょうか。
この“鐘の谷”で見せるラヴェルの素顔は、静謐さに満ちています。靄のかかった無人の谷にこだまする様々な鐘の響き。そして中間部には息の長い旋律。ラヴェルの真情が吐露されているようです。
ラヴェルは名作“ボレロ”などを書き上げている絶頂期の50台で、病気を発症しました。病名についてはいまだに論議を呼ぶところですが、大勢では「進行性失語症」と考えられています。痴呆はなく、作曲能力も失われず、ただ言語能力とともに楽譜を書いたり読んだりする能力がどんどん衰えていったようでした。1933年に素敵な歌曲を作曲した後3年余り、ラヴェルは一曲も作品を書いておりません。頭の中では音楽が鳴り響いていたというのに・・・じっと一日中椅子に座っているそのころのラヴェルに、ある女性が「何をしているの?」と聴いたところ、一言「待っている」と答えたそうです。
最後は脳腫瘍と誤診され、手術の数日後にラヴェルは世を去りました。
もちろん“鐘の谷”作曲時のラヴェルは元気だったわけですが、この静かに澄んだ響きを聴いていると、晩年の孤独なラヴェルの素顔が確かに見えるような気がします。
ムソルグスキー:展覧会の絵
後進国ロシアでは、我々がクラシック音楽と呼ぶところの西欧音楽が入ってきたのが18世紀になってからで、18世紀を生きたロシアの音楽家はみな、程度の差こそあれ西欧へのあこがれと自国の伝統的音楽を守るという、両方の狭間で揺れ動いて生きておりました。前者の立場の代表がチャイコフスキー(決してロシア的ではないというわけではないのですが)であるならば、後者の代表はムソルグスキー(1839-81)といっても過言ではないでしょう。
ムソルグスキーの仲間たち、俗に言うところのロシア五人組は、みなアマチュアで、他の仕事―多くは一種の専門職―を持っていました。バラキレフ(一時期役人をしていた)を指導者に、ムソルグスキー(下級士官)、キュイ(築城術の専門家である陸軍中将)、リムスキー=コルサコフ(高級官僚)、ボロディン(医学部出身の化学者)という具合です。彼らは一種の国策として普及してきた西欧化された音楽に対し、彼らが血の中に持っているロシア的なものを追求すべく試行錯誤していきました。いわば、音楽における「改革派」と呼ぶべき存在であり、「抵抗勢力」である大地主に保護された、西欧化された音楽を守る一派と厳しく対立しました。結果は、パトロンに恵まれ資金的に圧倒的優位に立つ「抵抗勢力」に対し、最初は厚い友情と鉄の結束を誇った五人組は分裂していってしまいます。
改革派の中でも音楽への入れ込み方がすさまじく、誰よりも多くのロシア人と「ロシア的なもの」を共有したいと願ったムソルグスキーが、その思いの純粋さと、思いを実現できる大きな才能のゆえに、仲間からさえも理解されなくなり最後は孤独と貧窮のうちに42歳の短い生涯を閉じたのは、なんと悲しいことでしょうか。死後の追悼文で、作曲家のイワノフは「彼ほどの才能があれば高い地位になれたのに、一人さびしく死んでいった・・・われらの才能ある人々を苦しめる運命とは一体何なのであろうか」と記しています。
そんなムソルグスキーにとって、画家・建築家のハルトマンは心を開いて語れる数少ない親友でした。正味3年しかなかったハルトマンとの友情はしかしハルトマンの39歳での急死という出来事によって閉じられます。ムソルグスキー34歳の時でした。ハルトマン急死の知らせを聞いたムソルグスキーは2日間茫然自失としていたと伝えられますが、共通の友人で評論家のスターソフにあてて「そこらにいる犬や猫だって生きているのに、なぜハルトマンは死ななくてはいけないのか」という悲痛な手紙を書いています。その心境察するに余りあります。
組曲「展覧会の絵」は、そんなハルトマンへの追悼と、未亡人の生活費援助のために企画された、ハルトマンの回顧展を見た印象を音楽にしたものです。近年ハルトマンの原画が再発見されるにつれ、ムソルグスキーが必ずしも絵を忠実に音楽に写し取ったのではなく、むしろ絵から受ける印象をかなり自由に膨らませて再構築した上で音楽にしたものだということがわかってきました。
“プロムナード(回廊)”を歩くムソルグスキー自身の姿から曲は始まります。悲しみをこらえながら歩くムソルグスキーの足取りは、5拍子と6拍子の交代によって多少もつれているようにも見えます。突然“グノームス(地の精の小人)”が目に飛び込んできます。原画はグロテスクながらヒョウキンな顔をしたくるみ割り人形のスケッチですが、音楽は異形の悲しみ、慟哭を表す激しいものになっております。中間に西欧音楽では「嘆き、悲しみ」を表す下降半音階が6オクターブの音域に渡って展開し、嘆きの深さを表現しています。最後はパチンというくるみ割りの音で音楽は終わります。
再び穏やかな“回廊”を歩いていくと、今度は“古い城”です。原画は同定されておりませんが、スターソフが絵について書いている「古い城の前に吟遊詩人が歌を歌っている」という構図を彷彿とさせる作品は複数見つかっております。いずれもハルトマンがイタリア旅行中に書いた絵です。昔の神話か、英雄伝説でも歌っているのでしょうか、吟遊詩人が物悲しくもハリのある歌声を響かせている遠景には、曲を通じて変わる事のない低音の持続が繰り返されます。それは、あたかも何が起きようとも歩みを止めない時の非情さをあらわしているようです。
気を取り直して“回廊”を歩めば、次は“チュイルリー”。自筆原稿には副題として(遊びの後の子供の諍い)と書かれています。原画はやはり見つかっておりませんが、ハルトマンがパリ旅行中に書いた子供たちの絵は残されております。音楽は必ずしもフランス風とは言えず、ムソルグスキーの自由なイマジネーションが発揮されております。
突然“ビドロ”が飛び込んできます。“ポーランド農民が使う牛車”という意味の、このタイトルを持つ原画は見つかっておりません。いきなりffで始まるそのインパクトは、ただ単に牛車が近づいて遠ざかる情景を描いただけとは考えられません。ムソルグスキーの目は、虐げられている農民の姿に注がれていたのでしょうか。
悲しい気持ちで“回廊”を進むと、今度はかわいらしい“卵の殻をつけたひよこの踊り”。これはバレエの衣装のためにハルトマンがデザインしたスケッチを元にしています。次いで“サミュエル・ゴールデンベルグとシュミュイル”。裕福なユダヤ人と貧乏なユダヤ人を描いているのですが、原画は別々の2枚の絵です。ムソルグスキーは単に絵に忠実であるということを超えて、2枚の絵からひとつのストーリー、楽曲を生み出したのでした。尊大な金持ちにキイキイ声で訴える貧乏人。争って見ても最後は金持ちの一喝で終わります。
ここで気分を持ち直して“回廊”を進みますと、次は“リモージュ。市場。”。原画は同定されておりませんが、パリ滞在中に見た市井のにぎやかな生活を描いたものでしょう。間髪いれず“カタコンベ”はローマ時代の地下墓地のことで、原画ではランプに照らされたハルトマンと思わしき、輪郭のはっきりしない人物などのほか、右側の暗がりにはしゃれこうべの並んだ棚が見られます。とはいえ、曲の劇的な嘆きぶりは原画を遥かに超える迫力で、楽譜に「ハルトマンの創造精神が訴えかけてくる」と書いてあるように、今まで抑制してきたムソルグスキーのハルトマンに対する慟哭の情が聴かれるようです。絵の印象に続き、後半には左手に“回廊”のモチーフのある悲しげなパートが書かれています。楽譜に「死者とともに、死者の言葉で」と書かれた部分です。
“鶏の足の上に立つ小屋(バーバ・ヤガー)”のバーバ・ヤガーとは、ロシア民謡によく出てくる魔女のことです。ユング派の精神分析によれば、女性的意識には、深層に包み込むイメージがあるそうですが、それが優しく包み込むということになれば例えば大地の母というようなものになり、何でも飲み込んでしまう恐ろしいものとなれば、鬼子母神のイメージになるというわけです。日本においてはヤマンバ(山姥)がまさにその両面を持つ存在です。バーバ・ヤガーはロシア版ヤマンバで、時に人助けをする優しさを持っていますが、大抵は何でも食べてしまう恐ろしい魔女として登場します。彼女はぴょんぴょん跳ね回る鶏の一本の足の上に建てられた小屋に住んでいるとされています。ハルトマンの原画は、時計のデザイン用にかなり図案化されて平面的に書かれており、おそらくぴょんぴょん跳ね回る鶏の足の曲想は、ムソルグスキーのイマジネーションから出てきたものでしょう。
最後に控えているのが“大きな門”です。コンペで一等賞になったハルトマンの原画は、しかし現実には建築されることなく終わりました。代わりにムソルグスキーが壮大な大門を音楽の上で建設したのです。幾百年と変わりなく建ち続け、そこを通っていくさまざまな人たち-出かけたまま帰らぬ人、戦争に行く人、お嫁に来る人などなど-を見守る大きな門。自らの信じる芸術に対する、一里塚の気持ちもあったのでしょうか・・・?
長い組曲ですが、配列はよく計算されています。5曲目の“ひよこの踊り”を折り返し点として、4曲目と6曲目は社会の底辺、3曲目と7曲目はフランスの市井の生活、2曲目と8曲目はイタリアの歴史、1曲目と9曲目はロシアの伝説、というように、テーマごとに整然と並んでいます。ロシアに始まりロシアに終わる、この並び方を見れば、ムソルグスキーがいかにこの組曲全体を緊密な結びつきで考えていたか窺えるような気がします。
尚、本日の演奏においては自筆譜ファクシミリを当たり、既版本と微妙に異なる部分については、音楽的意義を考えた上で採用しております。
展覧会の絵
プロムナード(回廊)
グノームス(土の精の小人;原題ラテン語)
(プロムナード)(原題なし)
古い城(原題イタリア語)
(プロムナード)(原題なし)
チュイルリー。遊びの後の子供の諍い(原題フランス語)
牛車(ポーランド語)
(プロムナード)(原題なし)
卵の殻をつけたひよこの踊り(原題ロシア語)
サムエル・ゴールデンベルグとシミュイル(ドイツ語)
プロムナード
リモージュ。市場。大ニュース。(原題フランス語)
カタコムベ(ローマの地下墓地:原題ラテン語)
(プロムナード)死者とともに、死者の言葉で
鶏の足に立つ小屋(バーバ・ヤガー)(原題ロシア語)
大きな門(首都キエフにある)(原題ロシア語)