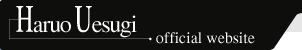
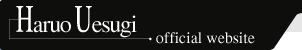 |
|
2007年11月24日 18:30開演 上杉春雄:バッハ平均律全曲連続演奏会2007 「バッハ 平均律クラヴィーア曲集第一巻」 バッハ 平均律クラヴィーア曲集第一巻空気が振動すると音が生まれます。今のピアノでは、真中のラは一秒間に大体440回振動していますが、この振動回数を2倍にすると一つ上のラの音になります。この振動数が1:2になる間隔を1オクターヴと言います。ラの音に対して2:3、すなわち3/2=1.5倍の振動数はミに、3:4の振動数はレの音になります。このように4:5,5:6・・・と単純整数比で音を作っていって、最終的に今のピアノの白い鍵盤、ドレミファソラシの7つと、黒い鍵盤5つの合計12音が1オクターヴの中に並ぶことになりました。 ここで、例えばラの音の1.5倍の振動数を積み重ねていくと、ラ→ミ→シ→・・・と、12個目にまたラが出てきますが、このラは、最初のラの7つ上、つまり2*2*・・・=128倍の振動数を持っているはずなのに、1.5を12回掛け合わせても128にはなりません。つまり、ラ→ミ→シ→・・・→ラと、ラ→ラ→・・・→ラとして出来た音(ラとラ)にはズレがあるのです。ヨーロッパの16世紀までの音楽は、主として人間の声のための音楽でしたから、その場でズレを調整できましたが、その後鍵盤楽器が使われるようなり、ハ長調のような白鍵が多い調性を基準にして音程を整えますと、このズレのために黒鍵を使う時の違和感が増えます。ズレを散らして違和感を少なくするように考案された音程の総称が「平均律」です。バッハが平均律の12の音全部に対して、長調・短調の曲を書いたのが、「平均律クラヴィーア曲集」で、2巻あわせて48曲からなります。平均化されたと言ってもバッハの時代にはまだズレは大きく、例えばハ長調とニ長調の雰囲気は違います。そういうこともよく考えてバッハは作曲しているのです。 フーガの多くは一つ、中には2つ稀に3つのテーマを持ち、それらが繰り返されます。テーマと対になる旋律もあり、テーマや対旋律の配置や、和音としての響きなどが厳密に考えられています。我々の周りでは、例えば水は高いところから低いところに落ちる、落ちれば速度が速くなる、などの物理法則に貫かれています。それら物理法則は地球上いたるところで厳密に貫かれています。僕には、このフーガという手法は、神の配慮としか思えぬほど精巧かつ厳密に作られたこの世界を、音楽で再現しようとしているように思います。そして、我々の肉体、精神、自然、世界、そして宇宙の森羅万象が、48曲を通して描かれているように感じられるのです。 第1曲 ハ長調 平易な前奏曲、テーマの出現密度が非常に濃いフーガからなっています。 前奏曲はサラバンドという荘重な踊りのリズムに乗って、歌と弦楽器の掛け合いが美しい曲です。真偽のほどはわかりませんが、バッハの最初の奥さんが死んだ直後に書かれた、という説もあります。3声のフーガは非常に凝った作りになっており、たった1つのテーマだけでほぼ全曲が構成されています。そのためにバッハは、テーマを2倍に引き伸ばす、上下をひっくり返す、リズムを変える、少しずつずらして3つ重ねる等、ありとあらゆる技法を投入しています。またそれだけの発展に耐えるだけの魅力が、このテーマにあるのも事実で、基音から下への引力に逆らって2回上昇しながらも、最後には力なく元に戻って気しまうというシンプルな音の動きの中に、人間の努力にもかかわらず自然も世界も何も変らない、というような、悲しい諦めが表現されているように感じられます。ニ短調では平凡、ホ短調では華やか過ぎ、という時に、嬰ニ短調で“ちょっとだけ”シャープに、痛切に、痛みを持って悲しみを表現されています。
ベートーヴェン ピアノソナタ30番 ホ長調 作品109 ピアノ曲史上最大の大曲、ソナタ29番「ハンマークラヴィーア」を完成させた後、ベートーヴェンは比較的小規模な3曲のピアノソナタを残しましたが、ベートーヴェンは決して大仕事の後の一服にこれらのソナタを書いたのではありません。3曲には、壮大な構想を3つの曲に振り分けたかのような共通点が見られます。30番と32番は、まず最終楽章が変奏曲であるという点、30番第一楽章第二主題の減七度和音は、そのまま32番の最初の音程になっています。30番と31番は、何よりその楽章構造が似ています。愛らしい第一楽章、疾走する第二楽章、そして第一・第二楽章に比べてアンバランスに長い第三楽章です。
ベートーヴェン ピアノソナタ31番 変イ長調 作品110 ベートーヴェンの“不滅の恋人”候補の筆頭Antonia Blentanoという女性に捧げようとしたとのことで(実際は献呈なし)、その頭文字AB(b)をそのまま曲の調性変イ(A♭)長調に当てた、という意見もあります。冒頭に“愛らしく、やさしく”と書かれた通り、30番譲りの長三度から始まる第一楽章はモーツァルトの典雅さを持っています。第二楽章ではメロディに「俺はだらしないぞ」という俗謡が使われていますが、緊迫感がある舞曲のリズムは、“死の舞踏”すらイメージさせます。一転、第三楽章では荘重なバロックの弦楽合奏から開始され、心の内を打ち明ける独白の後、Antoniaに呼びかけるように、A(ラ)の音が連打されますが、最後には声にならずに「嘆きの歌」になります。この歌は、バッハのヨハネ受難曲中のアリア「すべては終わった・ユダヤの英雄は輝かしい勝利とともにその闘いを止めた」と酷似しています。すべてが終わった後、新しい生命が芽生えるようにフーガが始まります。しかし志半ばにして再び「嘆きの歌」。吐く息も苦しげにあえぎながらも、尽きようとする命を燃やして必死に歌い継ぎます。ついに息絶えたようにみえたところから、最後のフーガ、そしてコーダ。不死鳥のように打ち続くどんな困難にも負けずに進む人間への共感と賛歌を歌い上げて、この俗謡―モーツァルト―バッハと、ベートーヴェンに至る音楽史を俯瞰する時の流れは終了するのです。
[ Top ] 当ウェブサイトでの内容は、上杉本人が責任を持って管理しております。 Copyright 2003 Haruo Uesugi All rights reserved. 許可なく転載を禁じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||